はじめに
こんにちは、kuronaです。
薬局で「ジェネリックにしますか?」と聞かれたことはありませんか?
価格が安いと聞くけれど、「本当に効くの?」「安全性は大丈夫?」と疑問に思う方も多いはずです。
ジェネリック医薬品は、患者さんの自己負担や家計に直結する大切なテーマです。この記事では、先発医薬品とジェネリック医薬品の違い、ジェネリックを選ぶメリットや注意点をわかりやすく整理します。
そもそも「先発医薬品」とは?
一般的な説明
先発医薬品は、新しく開発されて厚生労働省の承認を受け、最初に販売された「オリジナルの薬」です。
有効成分・効能・効果・用法用量が初めて世に出る薬を指します。
開発のプロセス
先発薬は動物実験から臨床試験(治験)まで数多くの試験を経て、安全性と有効性を確認したうえで承認されます。
研究から承認までには10年以上、数百億円規模の費用がかかることも珍しくありません
特許との関係
先発薬は特許で保護され、通常20年程度は独占的に販売可能です。
特許が切れると、他のメーカーも同じ有効成分を使った薬(=ジェネリック医薬品)を開発できるようになります。
「ジェネリック医薬品」とは?
一般的な説明
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発薬の特許が切れた後に製造・販売できる薬です。
有効成分は同じで、原則として効能・効果も同等。ただし、一部のジェネリックでは先発薬が持つすべての効能・効果を取得していない場合もあります。
特徴と違い
・添加物や製造方法が異なる:錠剤の大きさ、味、色、飲みやすさに差が出ることがあります。
・価格が安い:先発医薬品の2〜7割程度に抑えられることが多いです。
承認試験(生物学的同等性試験)
ジェネリックは新たに大規模な治験を行うのではなく、「先発薬と同じように体に取り込まれ、同じように効くか」を確認する試験を行います。
これは「生物学的同等性試験」と呼ばれ、服用後に血中濃度のカーブを測定し、先発薬とほぼ同じ範囲で一致すれば効果・安全性も同等と判断されます。
※ 薬の効き目は「血液中にどれくらい薬が溶けているか」で決まります。
先発薬とジェネリックでその推移が重なる=体での効き方も同じ、という考え方です。
先発医薬品とジェネリック医薬品の違い(比較表)
| 項目 | 先発医薬品 | ジェネリック医薬品 |
|---|---|---|
| 有効成分 | 同じ | 同じ |
| 効能・効果 | 全て取得 | 原則同じだが一部未取得もある |
| 添加物・剤形 | 固定 | 異なる場合あり(小型錠・味の改良など) |
| 開発 | 基礎研究・治験を経て承認 | 生物学的同等性試験で承認 |
| 薬価(費用) | 高め | 2〜7割安い |
| 特許 | 独占期間あり | 特許切れ後に開発可能 |
| データ量 | 豊富 | 同等性は確認済みだがデータは少なめ |
※有効成分は同じでも「価格」と「開発過程」が最大の違いです。
ジェネリック医薬品を選ぶメリット
費用が安い
ジェネリックは薬価が低く、長期的に薬を服用する患者さんの負担を軽減します。
また、国全体の医療費削減にもつながります。
飲みやすさの改善
ジェネリックには先発薬にはない工夫(小型錠、口腔内崩壊錠、味やにおいの改良)が施される場合があります。
高齢者や子どもでも飲みやすい形が選べるのは大きな利点です。
医療現場での普及と安心感
日本では処方せんに「後発品への変更可」欄が設けられ、厚労省も使用促進を進めています。
医師・薬剤師もジェネリックを積極的に推奨しています。
選択肢が広がる
同じ有効成分でも複数のメーカーが製造しており、剤形や飲みやすさを薬剤師と相談して選ぶことが可能です。
ジェネリック医薬品を選ぶ際の注意点
添加物や剤形の違い
有効成分は同じでも、添加物・色・大きさが異なるため、体質によっては合わない場合があります。
効能・効果の範囲が異なることがある
先発薬が持つすべての効能・効果をジェネリックが持っているとは限りません。
すべての薬にジェネリックがあるわけではない
新薬や一部の薬にはジェネリックが存在しない場合もあります。
複数メーカーによる違い
同じ有効成分でもメーカーごとに剤形や見た目が異なり、患者さんが混乱することがあります。
まとめ
・ジェネリック医薬品は、先発薬の特許が切れた後に製造・販売できる薬
・有効成分は同じで、効果・安全性は確認済み
・最大の違いは「価格」と「開発過程」
・メリットは「安さ」と「飲みやすさ」、注意点は「添加物や適応症の違い」
・最終的な選択は医師や薬剤師と相談することが大切
免責事項
本記事は、ジェネリック医薬品と先発医薬品の違いについて一般的な情報を整理したものであり、個々の症状や治療方針を示すものではありません。
実際に薬を選択・使用する際には、必ず医師・薬剤師などの専門家にご相談ください。
なお、当サイトの内容を参考にされたことによって生じたいかなるトラブルや損害についても、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
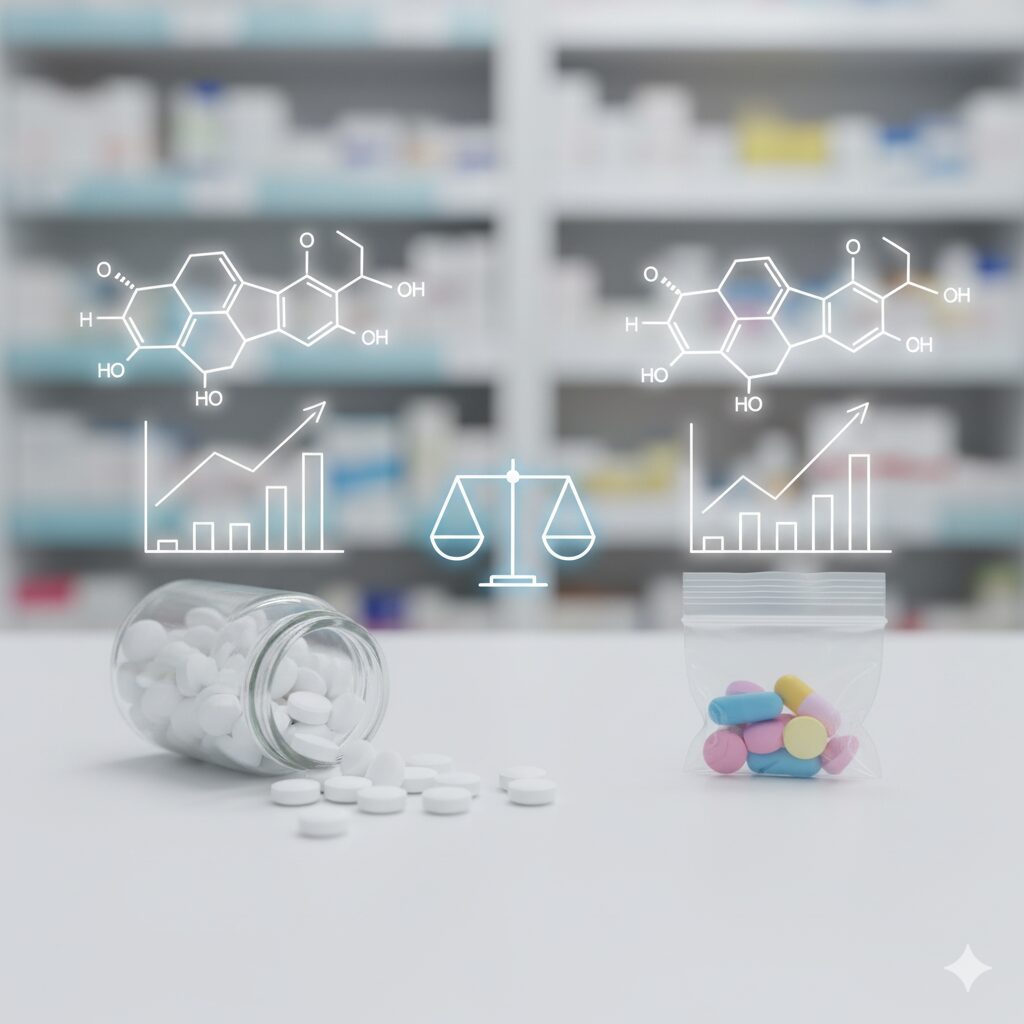


コメント